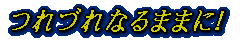
 しばらく更新してなかったけど、掲示板投稿に啓発されて
しばらく更新してなかったけど、掲示板投稿に啓発されて
「内木場城跡」探訪して来ました。
内木場城跡(宮崎県小林市大字東方字内木場)
小林より国道265号線を須木方面に向かう、
陰陽石バス停より左折、すぐに二股の別れ道を三ノ宮峡方面へ
しばらくすると左前方に小高い山が見える(内木場城跡)
陰陽石バス停より車で700㍍の距離。
最初は解らなかったが、たまたま近くでゲートボールをしている人々が
いたので、訪ねての発見である。
城跡の入り口には「内木場城跡」とあるだけで由来書き等の表示はない
車を止めて、徒歩で登る、すぐに頂上。
登り切った所は平坦になっており、恐らくここに本丸があったのであろう!
現在は畑になっており、特に城跡の痕跡はなく
城跡の表示がなければ見落としてしまう山林である。
周囲の人家を一巡り、山に向かって小さな神社があったが名称は表示されてない
近くに「内木場」姓を名乗る人家を2軒ほど発見。
 |
 |
| 国道265号、陰陽石入り口バス停。左折 |
分かれ道、右手、三ノ宮峡方面へ |
 |
 |
 |
 |
| 2005年4月16日撮影 |
城跡の頂上、恐らく本丸のあった所 |
 |
| 名称不明の神社 |
その後、図書館にて小林市史を調べてみる。以下の様に記されている。
| 内木場城跡(小林市大字東方字内木場) |
内木場城は木葉(きば)城ともいい、中世、真幸院の領主であった北原氏が築城したので
はないかと考えられている。
中央の高い台地が本丸。本丸と東出丸の間に空濠があり、西側の一番低い大地が西出丸。
西南を浜ノ瀬川がめぐる天然の要害となっている。
永禄年間(1560年代)橋口刑部左衛門が居城していたという。
「日向纂記」や「小林誌」には、元亀2年(1571)9月3日、内木場の砦を重ねて築き云々と
あり、伊東加賀守裕安が城を守ったが、木崎原合戦で戦死した。
天正4年(1576)以降、島津氏の領有となり、他の城と同様、
元和元年(1615)廃城となった。
小林市史より。
|
参考
木崎原合戦とは
小林市にある伊東氏の墓(伊東塚)
内木場城の近くにある小林城跡
内木場城跡の所在地図
ここをクリックして
宮崎県小林市東方3632
を入力すると付近の地図が出て来ます。
2005/4/16(土)
 もう2年目になる!
もう2年目になる!
中国の上海からきた女の子と知り合って
日本語の勉強に来ているのだが、
ジャパニース.パンダと言って私に馴染んでいる。
どうも、上海方面、つまり私にとっては
江南地方と言う方が歴史的に興味があるのだが・・・
去年、旅行の予定だつたが
行けずにいた、
上海から杭州、舟山諸島など、フリータイムで回って見たいと思っている、
ガイドは、いるのだけれど
今年こそは、実現しなくては・・・
2002/2/7(金)
 仕事にかまけと更新が?
仕事にかまけと更新が?
最近、旅行に行けないでいる。
仕事中心であつたり、資格試験勉強中であったりとか・・・
変わったことと言えば、このサイトの一部の紀行文が
電子本になる予定です。
また、旅行記とは関係なく、仕事を関連して書いたエッセイ集が
12月に文芸社より出版される事になりました。
題名は「わが輩はカネである」です。
お金に関するエッセイとおもしろネタですが
興味を覚えた方は、是非お読み下さい、
2001/11/9(金)
 サムライたちの海
サムライたちの海
NHK人間講座で「サムライたちの海」の講座が始まった。
講師は東アジアの海賊達をテーマにした小説家の白石一郎氏である。
第1回は8月7日放送で、古代の海賊王−藤原純友がテーマであった。
8回にわたつての火曜日11時からの放送です。
なかなかおもしろそうである。
これから村上水軍、松浦党、蒙古襲来など
テーマが続く、お見逃しのないように!
2001/8/10(金)
 「鉄砲記」の南浦文之を加治木に尋ねる。
「鉄砲記」の南浦文之を加治木に尋ねる。
鹿児島よりの帰り道、高速を加治木インターで下車する。
加治木は「鉄砲記」で有名な南浦文之の終焉の地である。
島津義久、義弘、家久の三代に仕えた外交、文教の最高顧問である。
中世の薩摩の精神的風土を作り上げた朱子学、
朱子学の流れをくむ薩南学派を天下に広めた人物でもある。
以前より、黒衣の外交官とも言われた文之の生涯を辿ることは、
島津の三州統一、そして琉球征伐へと繋がる思想的規範が
隠されている気がしていたからである。
文之の墓は、加治木インターの北にそびえる切り立った丘(加治木城跡)の
下方の安国寺の墓地にあった。
また、付近には龍門の滝があり、文之も訪れたであろう滝は
夏の日差しの中でひとときの涼を白く煙らせていた。
南浦文之の墓
2001/7/16(月)
 鑑真和上!ついに日本上陸。
鑑真和上!ついに日本上陸。
先日、テレビ番組の「世界ふしき発見」で、
鑑真和上が取り上げられた。
「不惜身命」の言葉とともに日本に味噌、納豆などの作り方など
を伝えた伝戒の師である。
6度目にして日本の地を踏んだ時は、盲目になつていた。
辿り着いたのは、鹿児島の秋目浦である。
テレビでは、ほとんど出なかったが、
2年前に坊津を旅行した時に、
「鑑真大和上まつり」を写真に収めた。
興味のある方は、坊津紀行「秋目編」へ
2001/2/18(日)
 知人が先日、石垣島(琉球諸島)の旅行から帰ってきた。
知人が先日、石垣島(琉球諸島)の旅行から帰ってきた。
日本の最南端に属する八重山列島。
石垣島、竹富島、黒島、小浜島、西表島、波照間島などからなる。
現地の古老の人達の言葉は、中国語みたいで全く解らないと言うことであつた。
台湾よりおよそ200キロ、日本本土より外国が近い。
一度は、行ってみたい所である。
沖縄から、久米島、宮古島、八重山諸島、台湾、中国福建省への道は
中世には、倭寇・海賊の海のルートであつた。
あちこちに倭寇遺跡が存在する。
南西諸島は、私のテーマであるけれども、なかなか旅行に行けない。
せめて資料整理でもと思って史跡資料室に
鹿児島市の琉球館跡と琉球人松を追加しました。
2001/1/18(木)
 新年、あけましておめでとうございます。
新年、あけましておめでとうございます。
いよいよ21世紀のスタート!
忙しさにかまけて資料整理が遅れ遅れに、
中国の歴史と日本の年表を作成中!
先日、中国よりメールが入った。日本の歴史に興味を持っている
と言うことで、歴史を勉強していると言うことである。
英語で来るので、当方もちょつと戸惑つてしまつたが、
なにせ、学生時代あまり頭のイイ方ではなかつたから?
中世の日本と中国の歴史が私のテーマですけど、
同じ様に、中国にも日本の歴史・文化に興味のある人がいると言うことで
うれしくなった。
今年は、絶対に中国へ行こうと目標を立てた。
みなさんも、今年が良い年でありますよう、
お祈り致します。
2001/1/1(月)
 関ヶ原の戦いの島津義弘の敵中突破は、何歳のとき?
関ヶ原の戦いの島津義弘の敵中突破は、何歳のとき?
今年は、関ヶ原の戦いより400年目にあたる。
義弘公ゆかりの地、えびの市文化会館で、
鹿児島の歴史資料館・尚古集成館、館長田村省三氏の講演があった。
(12月9日土曜日)
えびの市は今年市制30周年ということであつたが・・・
えびの市飯野は、島津義弘公が30歳より56歳までの26年間を
過ごした地でもある。
演題は「島津氏の内部事情と関ヶ原」であった。
義弘公は、85歳まで長生きしたこと、そして関ヶ原の時には、なんと
66歳であったこと、今の時代で考えても大変な歳である。
兵数わずか1000余名での家康本陣めがけての敵中突破!
島津豊久の身代わりによる戦死に支えながらも
帰鹿した時には、わずか拾数名であったと言われている。
演題の内容は、
1.関ヶ原の島津勢は、なぜ1000余名しかいなかったか?
豊臣秀吉の島津攻め、文禄・慶長の役と島津義久と義弘の関係。
2.文禄年間の島津における太閤検地の意味
3.島津義弘は、島津17代の当主であったか?
など、色々興味のある話であった。
ゆつくり、暇のある時に、その内容をまとめておきたい。
約2時間弱の講演であつた。
帰り通、伊東氏と島津氏の関ヶ原とも言われている木崎原の戦いの跡を訪ね、
さらに義弘公が1564年(文禄7年)11月に部下60人と共に
鹿児島・加世田より入った飯野城跡を訪ねた。
飯野城は義弘公が朝鮮出兵直前までの26間を過ごした城である。
写真等は、私の史跡資料室へ
2000/12/14(木)
 元寇の沈没船の一部発見!
元寇の沈没船の一部発見!
蒙古襲来、いわゆる元寇。元と高麗の連合軍が
文永の役(1274年)と弘安の役(1281年)の
2度にわたり日本へ襲来する。
その元寇の沈没船の一部と思われる木塊が
長崎・鷹島沖で発見されたとのこと。(12/6付新聞記事)
時代は、鎌倉時代・執権北条時宗の時代である。
来年のNHKの大河ドラマのテーマでもある。
元寇に対し鎌倉幕府は御家人をぞくぞくと北九州に下向させる。
南九州からも島津三代久経や、その子・忠宗、伊作島津家初代久長らが
箱崎に陣を構え、敵の来襲にそなえた。
弘安の役のころ、南九州の加世田では、
「モッコンコ、モッコンコ、竹下モッコンコ、ヒンラン、ヒンラン、夜も昼も鐘が鳴いどえた。」
「モツコンコ」とは蒙古の児、その蒙古が攻めてきて、夜も昼も鐘が鳴つた。
と言う意味で、現代の古老たちまで童謡として歌われた。とある。
(ふるさと加世田の史跡より)
その弘安の役では、元軍の船は暴風雨に遭い、鷹島沖で
艦船約4.400隻、将兵約14万人が全滅したと言われている。
元軍の船であることが確認されれば、
船体としては国内で初めてであると言うことである。
そして、この元寇こそが日本の倭寇を生んだとも言われている。
長崎・鷹島のあるホームページ
2000/12/6(水)
 今年も余すところ1ケ月
今年も余すところ1ケ月
あわただしい師走で、趣味のカメラ片手に
紅葉を追いかけ、ついでに歴史探訪も欠かさず
地元周辺の中世の山城跡を写真に収めた。
また、大坂の役のあとの家康の一国一城令により
取り壊されたものが多数であり、
有力大名の弱体化のために行われた政策ではあったが、
崩れ架けた石垣や土塁をみていると
400年ほど前のこととは言え、天守閣あたりを彩る紅葉が、
より一層、幽玄の世界へと誘ってくれる。
写真は正月休みでも、ゆっくりと整理しよう!
でも、今年の忘年会は12月に集中した!
去年は、11月の中旬からあった様な気がしたが、
世の中は、やはり不景気風が吹いている。
皆様!くれぐれも
ご自愛のほどを・・・・
2000/12/4(月)
 宮崎・国道268号線歴史探訪
宮崎・国道268号線歴史探訪
11月8日、宮崎まで仕事ついでに国道の歴史探訪。
身近な所にも、いろいろな史跡がある。
のんびりとではあつたが、道々に史跡を訪ねた。
野尻、紙屋、高岡、宮崎へ
国道268号線歴史探訪
2000/11/11(土)
 脇道にそれつつあるみたいだ!でもおもしろい。
脇道にそれつつあるみたいだ!でもおもしろい。
11月に入ったとは言え、最近、宮崎は暖かい
シャツ一枚で過ごせる。年々地球の温暖化が進んでいることを実感する。
11月には、中国の江南地方に旅行に行こうと思っていたが
今年は、どうやら行けそうにない。
いま、薩摩の琉球侵攻あたりの調べているが、
段々横道にそれている、薩摩の三州統一とか、秀吉の九州征服、
関ヶ原の戦いの前年に起こった、宮崎県都城の庄内の乱など
おもしろい、島津本家と一族の伊集院家との戦い
結局、家康の仲裁で戦いは終結するのだが・・・
その後、天下分け目の関ヶ原、島津義弘の敵陣の中央突破!
そして、1609年に島津家久の琉球侵攻につながってゆく
関ヶ原の戦いで西軍に付いた島津家、義久、義弘、家久とつながる時代は、
家康との駆け引きによつて、領地を失うことなく島津氏が生き延びた時代だけに、
またまた、おもしろい。その中で、智将と言われた16代義久に
興味が沸いてきている。機会を見付けて国分市にも、出向いてみようと
最近、またまた思っている。
2000/11/5(日)
 秋の夜長、また、一つの喜びに浸った。
秋の夜長、また、一つの喜びに浸った。
秋の夜長とは言え、時間に追われながら歴史書を読んだ。
なかなか、ホームページも更新出来ないまま時間だけが過ぎた。
調べるときりがないくらい時間が足りない
勿論、知りたい史料も足りない。
しかし、歴史を通じていろいろなものを学ぶ
過ぎ去った事を知ると言うことは、一見無意味なようなきがするが
これからの生き方に、一つの指標を与えてくれる。
いつの頃から、歴史好きになったか分からないが
最近!返す返す学生時代にもつと勉強しとけばよかったと反省する。
秋の夜長、反省と共に、知ることの喜びに浸っている。
その精か、あまり夜遊びに行かなくなつた。
ようやく、磯街道の続編・祇園之洲(ザビエル)を作り上げた。
興味のある方は、読んでやって下さい。
祇園之洲へ(ザビエル)
2000/10/25(水)
 今年2000年は、ザビエルが日本に上陸して451年目
今年2000年は、ザビエルが日本に上陸して451年目
1549年8月15日
ザビエルを薩摩に水先案内したヤジロウは、倭寇だつた?
その可能性は、十分にあるみたいだ!
調べてみたい。
そう言えば、さかのぼること6年前、
1543年、種子島に鉄砲が伝わった。この時、ポルトガル人の
乗っていた船は、中国人の倭寇・王直のジャンクである。
この時代の日本の海外文化移入は、
すべて倭寇が、係わっているようである!
ますます、調べる事が次々と起こってくる。
秋の夜長、まあ!ボチボチ行こう。
と思っている、今日この頃です。
2000/10/3(火)
 秋分の日
秋分の日
秋の彼岸の中日、すなわち日の出・日の入りが真東・真西にあり
昼と夜の長さが等しくなる日。
また、ご祖先を敬い、亡くなった人々をしのぶ日でもある。
今日の、宮崎地方は、秋晴れである。
父に言われて、浄信寺(浄土真宗派)に、
ご先祖様のお参りである。
久しぶりに、ありがたい説教を聞く!
ほとんど遅れて参加したのてどあるけれども、
一つだけイイ話を聞きました。
歴史的にと、言う事ですけど、
「おめでとう」の語源について、北海道からの住職の話によると、
「おめでとう」と漢字で書く時には「お目出とう!」
と一般的には、書くけれども、「お芽出とう!」と書いて欲しいと言う事です。
もともと、「おめでとう」と言う言葉は、
モンゴル地方の「オミトー」から来ていると言うことであり、
さらに、「オミトー」のルーツは?
やはり、インド!サンスクリツト語(梵語)であり、
「アミタ!」だそうです。
ミタとは、量を意味し、「アミタ」とは、量を計れないと言う意味であり、
この「アミタ!」が中国に渡り「アミダ!」に変化し、日本に伝わったと言う事で、
すなわち、この「アミダ!」こそ、「阿弥陀如来!」
あまねく照らす慈悲、押し測れない阿弥陀如来の、ご慈悲であると言う事だそうです。
皆様!、一同、合掌!
なんか、変な一人言になりましたけれど、たまにはイイ話聞くのも、イイかなぁ!と思いました。
これからは、[おめでとう!]と言う時には、この事を意識しょうと思ってます。
そう言えば、今日は私の宇都宮にいる姉の誕生日です。
としごの姉だけど、こころから[お芽出とう!]と言います。
照れくさくて、直接は言えないけどね、
あ!それと、今日、書きました!
[磯・街道探訪]
まだ、一部ですけど歴史に興味のある方、読んでください。
「多賀山公園」編です。
2000/9/23(日)
 海保白書、海賊対策初めて指摘。
海保白書、海賊対策初めて指摘。
12日、新聞の記事によると2000年版海上保安白書は、
海賊問題を初めて盛り込んだとのニュースである。
1999年10月マラッカ海峡で、日本人が襲撃された
貨物船「アロンドラ・レインボー」の事件がきっかけとなつたとの事であるが、
最近の海賊は、凶悪化し、船体や積み荷の売却を行う国際的犯罪組織の
存在が推測されるとしている。
マラツカは、ホルトガルによる占領(1551年)以前からも海の十字路と言われ
国際貿易の一大中心センターであった。
マラツカには、無数の国籍の人々が集まり、当時レケオと呼ばれたのは
琉球人のことであった。
また、海賊も当時から盛んに活動をしている。
その流れが、現代までも、脈々と続いていると言うことであろうか?
2000/9/13(水)
 鹿児島市、磯街道探訪。
鹿児島市、磯街道探訪。
9/5日より8日まで4日間の鹿児島出張である。と言うより講習会である。
その中日に、夕方より帰る途中に、旧道の磯街道を桜島を右手に眺めながら探訪する。
祇園之洲公園
多賀山公園
この一帯には、中世の山城、薩英戦争、東郷元帥墓地、ザビエル記念碑など
多くの遺跡がある。
詳細は、「磯街道探訪」へ
作成中です。
2000/9/7(木)
 夕暮れの海は、静かである。
夕暮れの海は、静かである。
志布志港は、南九州の国際物流の一大拠点として、現在も栄えている。
 |
| 大 隅 半 島(鹿児島県) |
西暦1342年(暦応5年)志布志湾の沖合いを30数隻の軍船が突き進んでいた。
四国、伊予の忽那(現在の中島)水軍と河野一族である。
船上の後醍醐帝の皇子、懷良(かねよし)親王は、征西将軍の勅命を受けて
南朝方勢力拡大と結集のための薩摩入りであった。
目指すは、南朝方の勢力拠点である指宿である。(山川港説が有力)
すでに、先駆けとして後醍醐帝の侍従、三条泰季(やすすえ)は5年前に下っている。
日本史上、天皇が南北に分かれて戦った南北朝時代。
光明天皇を擁立する足利尊氏の北朝と、
後醍醐帝の吉野朝の南朝方は、
以後全国規模で、南北朝合一(1392年)までの56年間の勢力争いを繰り返す。
当時、志布志には、湾を望む高台に松尾城があり、領主は救仁院(くにいん)氏から楡井(にれい)氏
畠山氏、新納(にいろ)氏、島津氏、肝付氏と移り変わった中世の山城であった。
また、志布志湾の南部に位置する高山町は、肝付氏の本城である高山城があり、
肝付氏は南朝方に組みし島津氏とは、長年の宿敵であつた。
以後、大隅地方は、島津氏の三州統一(日、隅、薩州)統一まで数々の戦いの舞台になってゆく。
倭寇の登場する南北朝動乱期や後期倭寇(応仁の乱以降)においては、
志布志港や高山の波見港は、大隅地方の倭寇の拠点であり、
波見港における重一族や堀口一族は、倭寇の頭目であつたと言われている。
16世紀以降の倭寇(武装した海商たち)は、遠く南方まで足を延ばし南シナ海までおよんでいる。
その多くの倭寇たちの拠点は、坊津をはじめとする南九州一帯の港であった。
嘉靖の大倭寇と言われる明の時代。
後期倭寇の代表は明人であり、長崎平戸に居を構えていた王直であった。
1543年(天文12年)ポルトガル人によって鉄砲が種子島にもたらされた時、通訳した五峰、その人である。
また、王直と共に初めより行動を共にしていた徐惟学の甥である徐海は、
僧侶であったが、ついに徐惟学を頼って海へ出た。
当時、徐海は徐惟学と共に大隅に滞在していた。
まもなく、中国沿海を荒らし回る倭寇の最大の賊首になってゆく。
そして、徐海軍団の腹心の辛五郎は、ここ大隅の人間であった。
特に、嘉靖の大倭寇と言われる1556年(嘉靖35年)における倭寇集団は、
およそ2万人であったと言われ、徐海自身も辛五郎を副将とし、
薩摩、大隅の倭人1万人余を引き連れて、
中国江南地方、抗州湾の北岸の乍浦(さほ)に上陸した。
次々と官軍を蹴散らし内陸へと侵入して行く、抗州へ至ろうとするが途中で負傷する。
また、官軍の智将、胡宋憲(こそうけん)の巧みな懐柔工作により最後を遂げる。
この時、副将の辛五郎も捕らえられたと言われている。
徐海にとつては、この大隅は第二の古里であったと言えるかも知れない。
また、薩摩における南方への進路は、遠く南シナまでおよんでいたと言われていたが、
当時、世界は大航海時代を迎えており、嘉靖年間にはポルトガルは、
インドのゴアを拠点とし、マラツカ、モルツカ諸島を占領し
中国折江省、寧波(にっぽう)の舟山群島まで達していた。
今こうして、インドネシアより来た二人の女の子と
夕暮れの志布志湾を眺めていると、何故か不思議な思いがしてくる。
彼女たちは知らないだろうが、遠い昔を辿れば、彼女たちにとつて
この志布志や薩摩地方は、なにかゆかりがあったに違いない。
この地方に働きに来た18歳と21歳の二人の女性、
その屈託のない笑い声や笑い顔を見ていると、
私にとっては、たまらなくいとおしくなってくる。
歴史好きが、そうさせるのか?
2000/9/3(日)
 書棚を整理していたら、3年前のフィリピン旅行のアルバムが出てきた。
書棚を整理していたら、3年前のフィリピン旅行のアルバムが出てきた。
フィリピンの友人の弟の結婚式に参加した時の写真である。
フィリピン諸島の中でも一番南に位置するミンダナオ島での結婚式である。
結婚式が終わって総勢10数名でダバオ沖のサマール島にキャンプした時の写真だ。
なつかしいと共に、
沖合は、海のキレイさに反し海賊でも出そうな感じであった。
近年、昭和36年、毎日新聞は、フィリピン・ダバオ沖に海賊が現れるを掲載した。
宝石など700万円を奪うとある。
また、マニラ湾では、昭和46年海賊に日本船員が襲われ重傷を負っている。
我々の宿泊したホテルには、常にショットガンを持ったガードマンが警備していた。
我々は、ダバオ市内を歩くときは、友人の兄に常に警備してもらった。
今でも、海賊は過去の歴史ではないことを実感する。
2000/9/1(金)
 以前からの知り合いのインドネシアの女性から電話がある。
以前からの知り合いのインドネシアの女性から電話がある。
志布志(鹿児島県)に来ているとのこと、私のテーマである倭寇の歴史。
志布志港は、関連がある所でもあり、遊びがてら休みの日でも行ってみようかと思う。
志布志(鹿児島県)公式ホームページ
2000/8/20(日)
 ひさしぶりに、ホームページをリニユーアル。
ひさしぶりに、ホームページをリニユーアル。
2000/8/15(火)
もどる







